職場の5Sをおさらいしましょう(あえて5s:sは小文字とします)
5sとは、職場の環境を整備し、業務効率を向上させるための「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの活動の頭文字をとったものです。それぞれのsが持つ意味は以下の通りです。
整理
必要なものと不要なものを区別し、不要なものを処分することです。
整頓
必要なものを、必要なときに、誰もがすぐに取り出せるように配置することです。
清掃
職場をきれいに掃除し、汚れのない状態を保つことです。
清潔
整理・整頓・清掃を維持し、常にきれいな状態を保つことです。
躾(しつけ)
決めたことを守るように習慣づけ、ルールを徹底することです…が、個人的には「しつこいくらいやること」としたいと思います。
簡単な話じゃないかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、実際に5s活動できてますか?
職場を「整理」することは、5sの最初のステップ
整理とは、必要なものを残して、不要になったものを適切に処分することをいいます。
法令、その他で保管期間が定められたものは、保管場所を決めてしっかり管理し、不要になった時には、溶解などの方法により処分します。
何でも保管すれば良いものではなく、不要であれば都度廃棄するよう、日ごろから心がけましょう。
整理を実践すれば、次の項目「整頓」に結びついていきます。
逆に言えば、整理できていなければ、次のステップに進むことができません。
職場を整理することは、5sの最初かつとても重要なステップなのです。
職場の「整頓」で生産性向上を図りましょう
職場の整理ができたら、次は「整頓」です。
整頓とは、職場の誰もが必要な時に必要なものを取り出せるようにしておくことを言います。
通常業務をこなしている時に、意識することはあまりないかと思います。
しかし、いざ内部監査・外部監査・業務監査・立ち入り検査などがあるときに、必要な資料がなかなか見つからない、データもどこに保存したかわからなくて、監査の際に慌てた経験を持つ方は非常に多いかと思います。
この原因の大半は、そもそも最初のステップである整理ができていないことに起因しています。
まずは、整理をしっかり実施して、そのうえで、書類の保管ルールや、データの保存ルールを決めていけば、整頓は割と楽に行うことができます。
整理・整頓までが整うと、書類やファイルを探す手間がなくなり、無駄がなくなることから、自然と業務効率化が図れることになります。
業務効率化=余計な仕事を作らない、無駄な業務プロセスをなくすと捉えると良いかと思います。
職場の清掃で、労災事故のリスクを減らしましょう
職場の清掃ですが、一番最初の項目にある「整理」を進めると、自ずと職場も清掃しやすい環境が整い、次の項目の「清潔」にもつながっていきます。
職場を清掃することで、床や棚に無駄なものがなくなり、棚からものが落ちたり、足元の荷物に足をぶつけたりするリスクが減ります。これは即ち、労働災害の予防にもつながります。
労働安全衛生法では、労働災害とは「業務上で生じた事故やケガ」を定義しています。
※労働者災害補償保険法で定義するものよりも広い意味があります。
仕事をする上で、事故やケガのリスクは避けたいところですし、せっかく仕事をするならば、できるだけ快適な環境で仕事をしたいですよね。
そう考えると、自然と、整理→整頓→清掃につながるものと考えられますね。
清潔とは、整理・整頓・清掃が行き届いた環境を継続することです
題目に示しましたが、「職場の清潔」とは、職場の整理・整頓・清掃が行き届いた状態を維持・継続することに尽きます。
また、清潔な職場を維持していれば、従業員も自然と清潔な身だしなみをするようになります。
整理・整頓・清掃・清潔が行き届いていない職場環境であれば、従業員が清潔を意識した身だしなみをしていなくても目立つことはありませんが、やはり清潔な職場環境が整っていたら、従業員も清潔な身だしなみをしないと目立ってしまうことから、清潔には職場の規律維持の意味合いも込められていると考えても良さそうですね。
職場のルールを決めて、しつこいくらい取り組みましょう
5sの最後は、「しつけ」と言われますが、私は「しつけ」よりも、「しつこいくらい継続すること」としたいと思います。
「しつけ」は、どうしても押しつけがましくなってしまうので、自分たちが主体的に4sをしつこいくらい継続して職場の文化として根付かせることで5sが達成されて、5sが達成されると「働きやすい職場環境が醸成される」と信じております。
5sが達成されると、下記のような効果が現れるかと思います。
地道な5sの継続が、大きな5Sを形成する
従業員が協力し合って、小さな5sを達成し、継続すると、以下のような大きな5Sが形成され、企業はもっと進化します!
Satisfy:従業員の職場満足度が向上する
Safety:労災事故の予防や、従業員の心理的安全性が向上する
Symphony:職場で決めたルールをしつこいくらい浸透させることで、調和が生まれる
Synergy:職場の調和が生まれることで、個々の強みが繋がってシナジー効果を生み出せる
Successful:結果として職場の成功体験が得られる
たかが5sとあなどらず、大きな5Sを目指した活動を!
従業員の皆が、5sを甘く見て実践しなければ、大きな5Sにはなりません。
毎日の小さな5s活動が、いつか大きな5Sになることを意識して、今一度5s活動について考えて実践してみませんか?
職場環境の改善を目指す事業所をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。


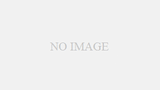

コメント